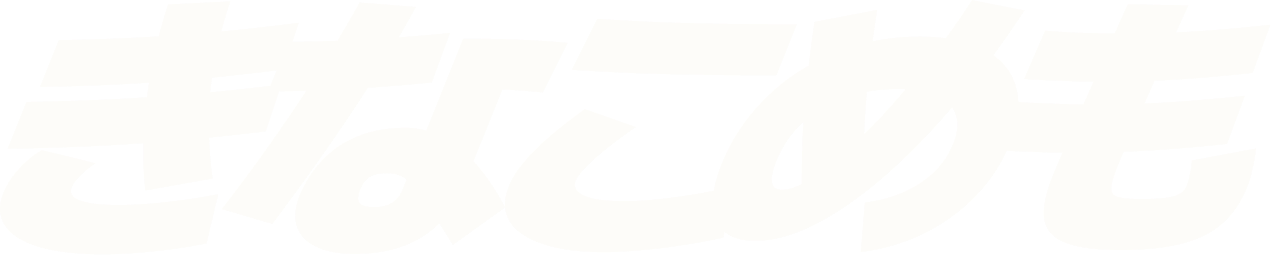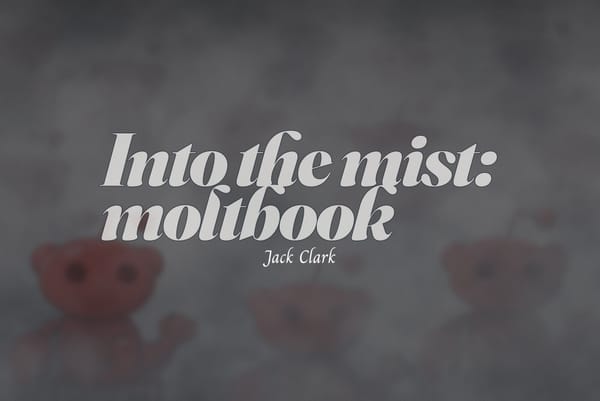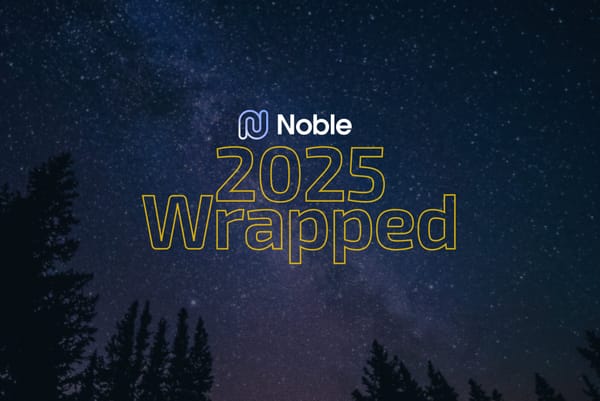Unichain – DeFi向けに設計されたEthereumのレイヤー2
Uniswap LabsによるUnichainのリリースブログ記事を和訳しました。

Uniswap LabsによるUnichainのリリースブログ記事を和訳しました。
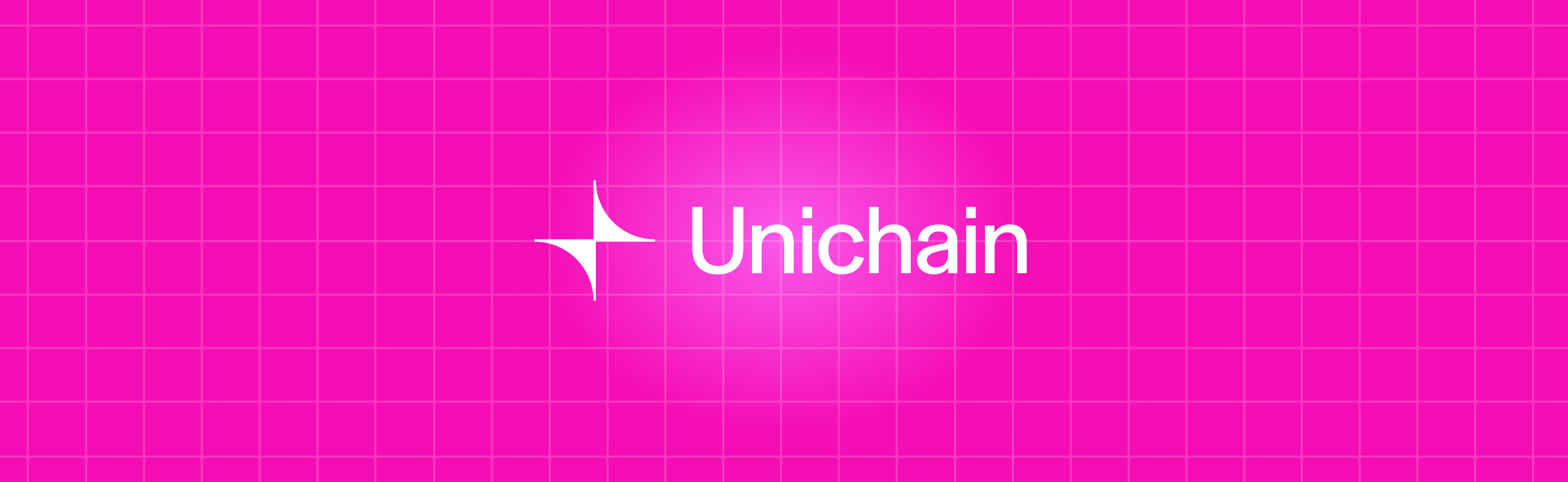
Uniswap Labsは、本日、Unichainを発表できることをとても嬉しく思います。これまで数年間、Uniswap LabsではDeFi製品の開発と拡大に取り組んできましたが、その中でDeFiの改善が必要な点やEthereumの拡張(スケーリング)を進めるために求められる要素を多く見つけました。そこで、今回私たちはUnichainを発表します。Unichainは、DeFiとマルチチェーン間の流動性のために設計された、スピーディで分散化された「Superchain L2(レイヤー2)」です。
DeFiの課題解決に向けて
分散型(DeFi)プロトコルは、まったく新しい金融システムを切り開いてきました。Uniswapプロトコルはその代表たるもので、過去6年間の取引量は2.4兆ドルにのぼり、ユーザー数は数百万人に拡大、累計5億件近い取引数を記録しています。ところが、Uniswapや他のDeFiプロトコルが大きく進化した一方で、Ethereum上のDeFiは依然として課題を抱えています。Unichainは、これらの問題を解決するための私たちの取り組みです。Unichainは以下の特長を備えています:
さらに分散化を進めながらも低コスト
分散化はDeFiにとって欠かせない要素です。Ethereumは非常に分散化されているため、L1(レイヤー1)の取引ではスピードやコストという点では妥協が必要とされています。そこで、Ethereumは2024年初めに「ロールアップ中心のロードマップ」の一環として、L2(レイヤー2)向けに安価なデータ提供を開始し、分散化を維持しながらスケーリングを進めようとしています。
Unichainは、このEthereumのスケーリング計画を活用・加速させるために設計されており、取引処理をL2に移すことで運用されます。具体的には、Unichainでは短期的にEthereum L1と比較して取引コストを約95%削減し、将来的にはさらなるコスト低減を目指しています。
まもなく、Unichainはノードがブロックを検証できる分散型バリデーションネットワークを導入する予定です。これにより、ファイナリティ(最終性)の確保が一層強化され、矛盾したブロックや無効なブロックが発生するリスクが軽減されます。
高速で、ほぼ即時のトレード
次世代のマーケットをオンチェーンで実現するには、DeFiの速度向上が不可欠です。Unichainは、1秒ごとにブロックを生成する構造でローンチし、さらに250ミリ秒の「サブブロック」を導入する予定で、これによりユーザーは即時のトレードを体感できるようになります。ブロック生成が速くなることでマーケットの効率も向上し、MEV(マイナー抽出可能価値)による価値の損失も軽減されます。
この改善は、Flashbotsとの協力で開発された「信頼実行環境(TEE)」を利用するブロックビルダーによって実現します。TEEは、トレードの速度向上だけでなく、トレード順序の透明性を高め、失敗するトレードの発生を防ぐよう設計されています。
TEEは分散型のコンセンサス(合意形成)を完全に代替するものではありませんが、他のブロックビルダーと比べて信頼性やセキュリティを大幅に強化できる利点があります。
シームレスなマルチチェーン・スワッピング
Ethereumのスケーリング・ロードマップが進むにつれ、多くのL2が登場してきます。既にこの動きは顕著で、新たなL2はコストを削減を実現しているものの、流動性を分散させ、ユーザーエクスペリエンスが複雑になるという課題も生んでいます。Unichainは、ユーザーがどのチェーンを使っているかに関係なく、シームレスにスワッピングを利用できるよう設計されています。
Optimism Superchainの一部として、UnichainはOP Labsと提携し、SuperchainのL2間で「単一ブロックでのクロスチェーン・メッセージ送信」が可能になるネイティブな相互運用性(インターオペラビリティ)を実現しています。また、Superchain外のチェーンとの相互運用性向上のため、ERC-7683などの取り組みも進めており、ユーザーがチェーンの違いを気にせずスムーズに使える環境を目指しています。
クロスチェーンの流動性は、ユーザーがアクセスしやすいシンプルで直感的なインターフェースと組み合わさることで、さらに大きな影響をもたらします。Unichainのローンチ後、UniswapインターフェースやUniswapウォレットにクロスチェーン・スワッピング機能を追加する予定です。
Unichainの詳細なアーキテクチャについては、Unichainのホワイトペーパーをご覧ください。
💡 こちらからUnichainホワイトペーパーの日本語訳に飛べます
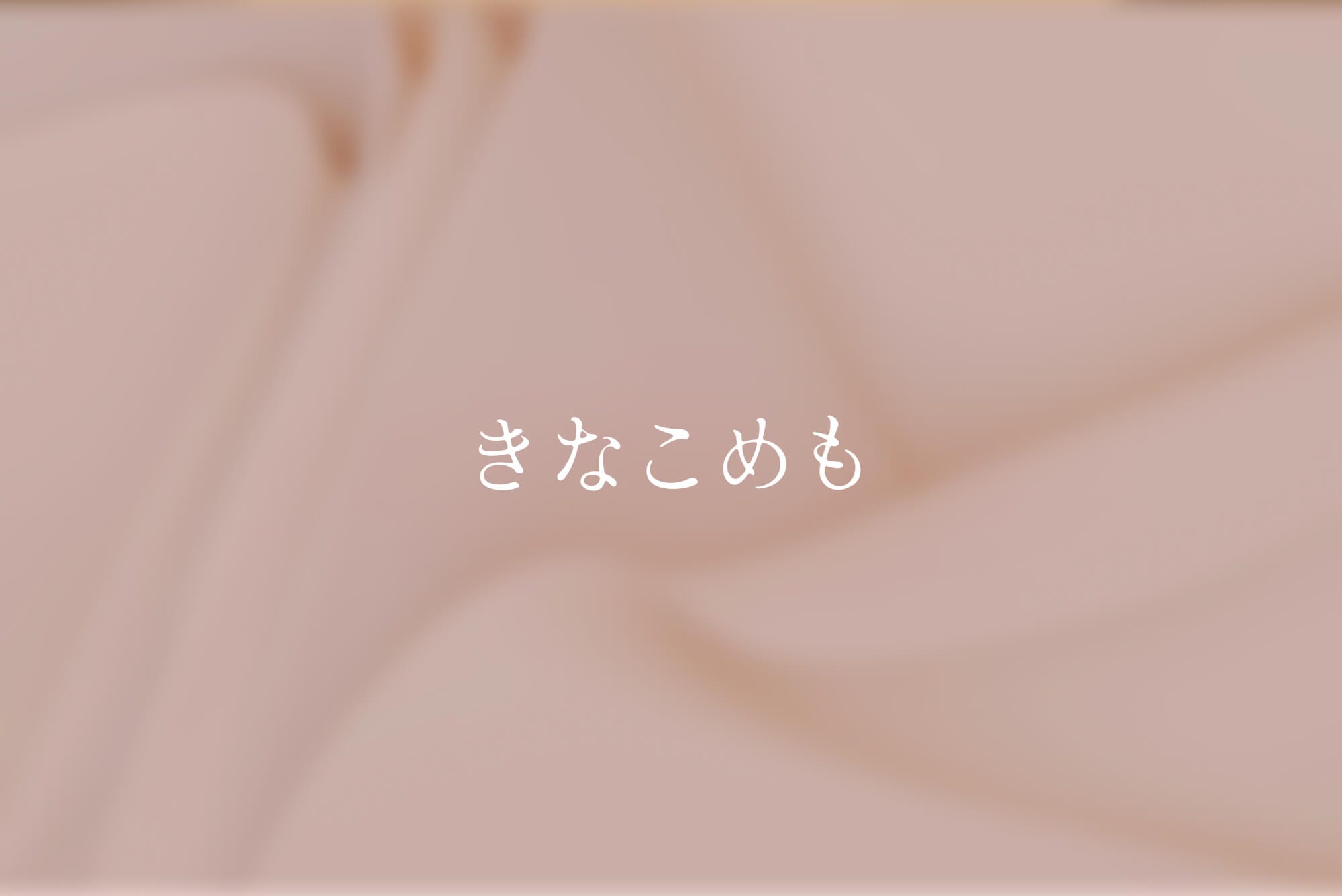
共にEthereumのスケーリングを進めよう
これはまだ始まりに過ぎません。Unichainはモジュール構造で設計されており、TEEベースのブロックビルダーやバリデーションネットワークといった機能を拡張し、さらなる分散化やユーザーエクスペリエンスの向上を目指した新しい機能を取り入れることが可能です。
Unichainは、ブロックビルダーやノードソフトウェアも含め、MITライセンスのもとでオープンソース化されており、他のチェーンも採用できるようになっています。Uniswap LabsはEthereumのスケーリングに貢献するため、OP Stackの主要開発者にも加わります。
Unichainでの開発を始めよう
私たちは、幅広いコミュニティの皆さんがUnichainに参加することを心待ちにしています。本日、Unichainのテストネットが公開され、今年中にメインネットもローンチ予定です。開発者は、Unichain Builder Toolkitに含まれる豊富なリソースを自由に活用できるようになりました。また、Uniswap Foundationは開発者の支援に力を入れており、Unichainでの開発を進めるための助成金やプログラムを提供しています。
参加するには:
- 詳細を確認し、開発者向けドキュメントを unichain.org でチェック
- テストネットでデプロイ
- Uniswap Foundationからの開発者助成金に応募するため、Builder Open Callフォームを記入する
- Unichainテストネットに資産をブリッジし、Uniswapインターフェースでスワップを体験
- Unichainホワイトペーパーにリンクされているリポジトリに貢献
最新情報は、Twitterで@Unichainをフォローするか、Discord内の#unichainチャンネルに参加してご確認ください。
Unichain情報
Webサイト:https://www.unichain.org/
X(Twitter):https://x.com/unichain
Uniswapと共通のブログ:https://blog.uniswap.org/